偉大なるベーシスト、ジョー・オズボーンが亡くなった。
個人的に色々な想いがあり過ぎて何から書いていいのか分からないが、勝手にジョー・オズボーン・マニアを自称する私、備忘録的にも書き留めておこうと思う。
彼の名前を知らなくても、彼の奏でた音を知らなくても、音楽に詳しくなくても、今この記事を読んでいる皆さんは、きっと知らないうちに彼の演奏を聴いている。
そう言い切れるほど、彼の残した功績にはあまりにも大きい。

Contents
ストーリー
1937年8月28日ルイジアナ州生まれ。
12歳からギターを始め、1957年からプロのギタリストとしてデビュー。
最初のロックンロール・ベーシストと言っても過言ではないキャリアの持ち主で、ロックに限らずポップスからカントリーまで幅広く活躍。
今の時代、YouTubeなどで当時の映像を確認することが出来るのは歴史的資料としての価値が大きい。
ラスベガスで働いていたジョーがベースを手にし、西海岸へ。
約1年間プレイするものの、その後故郷のルイジアナに戻ったところで、リック・ネルソンが
ヒットさせた『Travelin’ Man』はジョーの進言があったようだ。
バックでリーゼントスタイルのジョーの姿が確認出来うる最も古い映像だろうか。
64年にリッキーとの仕事を終えると、旧知の仲であったロックンローラー、ジョニー・リバースと本格的に仕事を始める。
ビートルズが旋風を巻き起こす、ほんの少し前の出来事だ。
いわゆる”レッキング・クルー”と呼ばれたスタジオ・ミュージシャン集団の一人だが、ダンヒル・リズム・セクションと呼ばれたハル・ブレイン(ドラマーであり、レッキング・クルーの中でもリーダー格のプレイヤー。カーペンターズをはじめ、エルヴィス・プレスリー、フランク・シナトラ、ビーチ・ボーイズ、サイモン&ガーファンクル、フィフス・ディメンション、モンキーズなどの作品に参加)やラリー・ネクテル(キーボーディストとして主に活躍するが、ジョーと同じくベースも弾くため、ベーシストとしてクレジットされていることも多い。サイモン&ガーファンクルにおける『明日に架ける橋』のピアノは白眉のプレイ)と組んでいたトライアングル・リズムでの仕事の方が有名だろうか。
ジャン&ディーンのマネージャーだったルー・アドラーと仕事をしていたジョーだが、ハル&ラリーと仕事を始めたのはこの頃だという。
ダンヒル・リズム・セクションはルー・アドラーのお気に入りで、彼が関わるものにはもれなく呼ばれていたそうだ。
また、そこでエンジニアをしていたのが、後に大プロデューサーとなるボーンズ・ハウである。
最初はコードが書いてあるリード・シートを読む事も出来なかったジョーが、トミー・テデスコからのアドバイスもあり、書籍で勉強したらしい。その結果、それまで以上にジョーには依頼が殺到したそうである。
既に1stコールなっていたジョーは3時間で3〜4曲、時々6曲ぐらいのペースで録っていた。
ブリティッシュ・インヴェイジョンと言われるブームが起きた時でさえ、来る者は拒まずの姿勢で仕事を受けていたという。
その結果、1時間45ドルだったギャランティーは130ドルまでに登り、それでも以来が途切れず2倍の金額を請求したが、さらに依頼が来る日々。
1日2回のセッションを週に6日、時には日曜日も含めてという状態の中で1974年、多忙を極めるスケジュールに嫌気が差しL.A.を離れてナッシュビルに移り住んだ。
全米トップ40には、なんと200を超えるヒット曲の演奏に参加。
1位を獲得した曲は18曲、カントリー・チャートでは、なんと53曲ものNo.1ヒット曲でプレイしてるというのだから偉人である。
参加したグループは数知れず。
ざっと名前を挙げれば、先ほどのリック・ネルソンをはじめとしてジョニー・リバース、ハーブ・アルバート、グループならばモンキーズやママス&パパス、フィフス・ディメンション、アソシエイション、グラスルーツ、アメリカなど錚々たる名前が並ぶ。

しかしジョーといえば、何と言ってもカーペンターズとサイモン&ガーファンクルでの仕事が有名。
そう、我々ナイフラ・・・私と小池が多大に影響受けているサウンドそのものなのだ。
特にカーペンターズはプロ・デビュー前、いち早くカレンの歌声と兄妹のハーモニーに目を付け、当時でも珍しい自身のレーベルを通じて自宅ガレージを開放、デモ制作に一役買っていたこともあるが、アルバムでもほとんどはジョーがベースを弾いている。
ツアーこそサックス兼ベーシストでもあるボブ・メッセンジャーが弾いているが、その後の彼らが文字どおりスーパースターになっていっても変わらずスタジオで起用されるベーシストは、いつもジョーだった。
リチャードによれば、ジョーのベースには指示がほとんどせず、ただ弾きたいように任せていただけだという。
ジョーのベースが入れば楽曲に抜群の安定感をもたらす。
単体で聴くと変わったサウンドに思えるかも知れないが、キックと噛み合った瞬間、とてつもない心地よさを生み出す低音になるのだ。
ジョーの愛した機材
きっと、日本で唯一の専門誌と謳っているベースマガジンも取り上げてくれないだろうから、代わりに書いておく。
ギタリスト時代はGibson ES-176やFender Telecasterなども愛用したようである。
彼の愛機で有名なのは60年製のFender J-Bass(一部61年製説あるが、ジョー自身が60年製と証言している)をリック・ネルソンとの仕事している時代に手に入れた。
だが、意外にも最初期の頃はKayのベースに始まり、P-Bass(恐らく58年製だろうか)を使用していたようである。
初めて見たJ-Bassに戸惑いを感じながらも、P-Bassに比べてネックが薄いことからもフィンガリングが楽になるだろうと考えた。
以来、その1本が彼の愛機となる。

今でも根強く人気がある2スタック・ノブのタイプで、ボディーはアルダー、カラーはサンバースト。
そこに62年に張ってから交換していないというラ・ベラのヘヴィーゲージを使用した丸く太い、ふくよかな低音。
ピックはFenderのHeavyを用いてピック弾き独特のアタックが強烈に出ている。
これはピックアップ・フェンスの上に右手を置き、フロント部分をピッキングすることでしか生まれないサウンド。
ジョーの弾き方はどんなジャンル、ミュージシャンでも一貫してこのスタイルだ。
真ん中やリアでのピッキングでは絶対出ないサウンドで、”こねくりまわす”と言われる手首の使い方が個性的。
通常、ギターとベースは弾き方が異なるが、ジョーの場合は独学で音楽に触れていたことから、ギタリスト的な弾き方ともまた違う、円を描くような独特なフォーム。
細かい話になるが、ピッキングする瞬間に力を入れて振り抜くスタイルというより、弦に擦り付けてピックが通過するイメージだ。
元々ギタリストであったことも関係してるのだろうが、この時代(というより、彼らよりエレクトリックにおいて上の世代がいない)で既にピック弾きのベーシストがいるのだから、ベース=指弾きの概念はおかしいと筆者は声を大にして言いたい。
一晩中、ベースとギター両方を演奏するジョーにとって、ピック弾きというのはある意味自然で、それが持ち前のサウンドを決定づけた要因である。
アンプはFender Concert ampを使用。

究極の歌伴ベースとも言えるプレイ
当時は機材も発達していないので、そのままだとこもるようなサウンドしか出ない、録れないのだが、それを解消するため、アンプのセッティングではトレブルを相当上げていたようだ。
しかし、リア・ピックアップ(ジョーは”トレブル・ピックアップ”と呼んでいた)は使用しない。
ミドルが多過ぎるサウンドは好みでなかったようだ。
レコーディング方法もアンプのみから、DI(ダイレクト・インジェクションボックス)が登場してから両方使うのが主流となる。
ジョーのこだわり
私はカーペンターズでジョーが弾いた楽曲の全てを譜面に起こし、ピッキングのニュアンスまで完全にコピー出来るよう解析した時期があるが、ベースラインの大きな特徴の1つとして「4弦を使用しない」というのは現代から考えると衝撃的。
「頑な」とも思えるぐらい、4弦のフレーズが登場しないのだ。
譜面を見ただけで、明らかに避けているのが分かるのだ。(詳しい耳コピ方法はこちら)
以前、ベース・マガジンでも語っていたが「4弦のサウンドが気に入らなかったから」というのが理由だそうだが、これにはワケがある。
ジョーは先述したラ・ベラのヘヴィーゲージの弦を張っていたためネックの状態が悪く、順反りの状態であったことが関係していると思われる(サスティンのない4弦のトーンが嫌いだったとか)。
従ってA(4弦5f)より下、Eまでのコードを弾く時は、必ずと言ってもいいぐらい2弦を選択している。
つまり4弦の1〜5fまでの音を使うときは、ほぼオクターヴ上で弾いているというわけだ。
全体の95%ぐらいは傾向として2弦を選択しているので、譜面を見ているだけでも、あながちジョーが4弦を”意図的に避けていた”というのは間違いではない事を立証する証拠である。
しかも62年から張っているこの弦は全く新しいものに変えず張りっぱなしとも語っていた。
モータウンのジェームス・ジェマーソンのように、ジョーもまた枯れたサウンドが好みだったのかも知れない。
フレーズについて
歌を活かすために「静」と「動」の使い分け
得意技その1 スライドとグリスのニュアンスで色気のあるライン
ベース・ラインではニュアンスのつけ方にもかなり癖がある(ここもジョーの大きな特徴)。
定番のツーファイブ進行などの時、キーDにおいて例えばEm→Aなどの時は2弦2フレットからスライドを必ず混じえて2弦7フレットへシフトするのだ。
オクターヴ下のAを使いたい時は先程のルールに基づき4弦5fではなく3弦の開放を選択。
ベースで一番響くキーはGだと思うが、コードとしても頻繁によく出てくるGでも迷わず2弦5フレットを選択。そうすると、次に進む音は決まってその下のDを選択する。
3拍目のウラでルートのオクターブ上や1弦を使用すること、さらにスライドとグリスを多用すること。
ルートから5th、オクターヴ上のルートという定番もよく使うが、そこにシンコペーションを混ぜて8分ウラ、もしくは16分ウラに引っ掛けるように弾くのも特徴。
進む順番も例えばコードDのフレーズならば
3弦5f(ルート)→2弦7f(5th)→1弦7f(オクターヴ上のルート)
という定番の動き。ジョーの場合、この2弦7fのAや1弦7fのDノートを弾くときにウラのリズムではめ込んでくるということだ。
さらに最後の1弦7fはかなり高確率でグリス・ダウンする。
さらにニュアンスを付けたい時にはDノートを弾く直前に5fないし6f付近から小さくスライドを入れてしゃくり上げて、オンリズムで7fを弾き、同時にグリス・ダウンするといった色気タップリのフレーズを入れるのだ。
たかだか1弦7fのたった1音弾くだけなのに「前後にスライド(それも長さの違う)2つを入れる」という、これが気持ち、感情を込めて弾く歌伴の模範となる要素である。
こういう部分もベースを弾く上で「重要なテクニックの1つ」と私は考える。
一般的に地味なテクニック(私は逆に豪快だと思っているが)だと思われがちだが、とんでもない!
ベースという楽器は、つくづくこういう部分がモノをいうんだ、というのが私の考えであるが、左手が早く動くことより、音数を詰めることよりも重要度は高いテクニックだと思う。
こう言った部分は注意深く聴かないと、そのまま聴き逃すところなので気づかない人が多く、この辺りがジョー・オズボーンというプレイヤーが過少評価されている要因ではないかと思う。
譜面にすると、いちいちスライドのニュアンスを書き込まなければならないので、実際のところ、ジョーがプレイしている楽曲のベース・ラインをスコアで確認すると相当簡略化されていることに気づく。
また、音価同様「どれぐらい粘るのか」とスライドに移るまでの長さや、スライドするスピード、切り方などで、その人の個性が出るのだ。
ここをおざなりにしては、気持ちのこもったプレイは残せない。
私がジョー・オズボーンが好きなのは、シンプル、豪快ながらも隅々まで非常に丁寧にプレイしている点で、これだけセッション数が多いのに、いい加減なやっつけ仕事をしている感じが見当たらないところだ。
まさにベースを弾く職人である。
レッキング・クルーの証言によれば彼はレコーディング中、間違えることが極端に少なく、その辺りでも信頼を得ていたようだが、同じセクションを繰り返すような曲でも「全てが同じように聴こえてリズムをズラすなどして1回目と2回目で微妙な違いを付ける」ことが多い。
日本人のプレイヤーだと細野晴臣さんなどもそうだが、特にロックやポップスの場合はリピートして全く同じセクションを繰り返すことが構成上多いが、そう考えると100%決め打ちしてプレイするというよりコードだけを見て反射的に弾いている可能性が高い。
さらに特徴を挙げるならば
9thにはグリスを用いてハンマリング的な弾き方、さらにピッキングせずにグリス・ダウン。
ジョーの大きな武器であるグリスやスライドは、ただのアップ、ダウンではなく、1度のピッキングでアップダウンを連続して行うことである。
さらにもう一度ピッキングして同じくグリス(スライド)のアップダウンを行うという連続技などもかなりの確率で披露されている。Carpenters『I Just Fall In Love Again』
ここがかなり色気のある、味のあるジョーらしいベース・サウンドに繋がっているのだ。
そうかと思えば、バラードでも1拍目の頭と2拍目ウラしか弾かないという、リズムをかなり大きく取っているにも関わらず、豪快にスライドを混ぜてくる。
スラップなどもやってしまう若いベーシストにこの連続技を弾かせてみると案外弾けないことが多い。
試しに歴史的名曲『Yesterday Once More』を聴いてみてほしい。2Aから入るフレーズ、歌と鍵盤しか他の楽器はいないのだが、ハイ・ポジションをスライドとグリスを交えながら歌メロによく絡んでいて、それでも邪魔をしない、そしてベースラインだけ切り取ってもかなりエロいサウンドを聴かせてくれている。
譜面上では簡単に見えるのだが、スライドのアップ&ダウンのスピードが決め手なので(ここが簡単にコピー出来ない所以)ジョーのベースにはこういった譜面に書き表せないニュアンスがふんだんに含まれているのだ。
得意技その2 楽曲に安定感を与えるライン
得意フレーズはルートと5thを行ったり来たりしながら、リズムを崩したりする典型的なカントリーのスタイルだ。
リズムとしては1〜4拍目頭をスタッカートで切ってプレイするカントリー・スタイルか、付点16分(速いとサンバのリズム)をレガート”気味”に(小さく休符が入る)プレイ。
場合によっては16分のウラウラはゴースト・ノート”気味”に弾く場合もあり。
得意技その3 グルーヴィーにプレイ
スケールを使用する時、ランニングする時はメジャー・スケールを多用することがほとんどである。
コードのみを意識していると、ルートの次はつい3rdに行きたくなるが、ジョーの場合は9thを通過する。
ルート→9th→3rd→ルートは、ジョーの専売特許のようなフレーズ。
その前にシェイクのリズムを入れ、1拍目は若干切り気味に弾けば黄金フレーズの完成。
そしてメジャー感の明るさを出す6thの使い方も特徴。
この6thや9thというのは使いやすいので非常に便利なサウンドだ。
得意技その4 リズムを強調するライン
スピード感ある曲の時はシェイクのリズムを多用。その際、1拍目の頭はレガートせず、ファンクのように切ってしまう。
得意技その5 トリッキーなライン
シンプルにシンコペさせる時はウラ、ウラ、ウラ、ウラと連続で弾く事もある。
特に頭でスネアやアコギでリズムを刻む時に敢えて自身のリズムは外してグルーヴ感を出すのだ。Simon&Garfunkel『A Hazy Shade Of Winter』
さらにグルーヴさせる時は、そのシンコペーションをさらに16分で混ぜて複雑化させる。
真骨頂はフィフス・ディメンションの『Aquarius』
ジョーの話によればフィフス・ディメンションの場合、ほとんどの曲にリズム譜が既に存在していて、この曲にもベース・ラインが書いてあったが、プロデューサーからの要望で、もっと複雑にプレイしてくれとのリクエストがあったらしい。
その際に自分自身で最適だと思うラインを演奏しただけ、とも語っている。
つまり、最初から決められたフレーズでもなければ、決め打ちして練習したわけでもない事を物語っているのがよく分かるエピソードだ。
ベース・ソロ的な雰囲気もありつつ、歌モノとして決して破綻をきたさないようなセンスは脱帽の一言。
レッキング・クルーのDVDを観ていただきたい。この部分のみを捉えた、巧みにオルタネイトするジョーのピッキング姿がソロで観られる貴重な映像だ。
ちなみに、原曲とは若干違うラインでプレイしてるが、あまりにも昔の曲で忘れているのか、それでも先程の検証裏付けるかのように反射的に弾く姿が確認出来る。

最後にお薦め定番曲を紹介したい。
Association『Everything That Touches You』
Simon&Garfunkel『America』『Bridge Over Trailed Water』『The Only Living Boy In New York』
Carpenters 全部。と、言いたいがベスト的な曲だけでも相当すごいベースが聴けるので、ベーシストは必聴。
60〜70年代のアメリカン・ポップス・・・・もっと言えば、A&Mのサウンドをベースとしたザ・ナイト・フライヤーというバンドにおいて、私はこれからもずっとジョー・オズボーンが教えてくれたスタイルを追求するだろう。
参考資料:Vintage Guitar Magazine
ジョーのラインを完コピしてみました。
ザ・ナイト・フライヤー カーペンターズcover
「Yesterday Once More」
モッズ野郎サガワトモユキが参加するポップスバンド、ザ・ナイト・フライヤー(通称:ナイフラ)関連ページはこちらからどうぞ。60’Sアメリカン・ポップス、フレンチ・ポップス、AOR、MOR、シティ・ポップス、ソフト・ロックファンへ贈る!!
ナイフラOfficial HP

ナイフラOfficial YouTubeチャンネル「ナイフラチャンネル」
ナイフラOfficial twitter https://twitter.com/the_night_flyer
ナイフラOfficial Blog http://ameblo.jp/thenightflyer/
毎回ナイフラの最新情報が届くメルマガ登録、ライブチケット予約、お問い合わせ、メンバーへの質問コーナー「ナイフラQ」もこちらへ↓

ベーシスト・サガワのちょー優しいベースレッスン、お仕事のご依頼、お問い合わせはこちら
info.sagaworksあっとじーメール
d-i-musicどっとcom/info

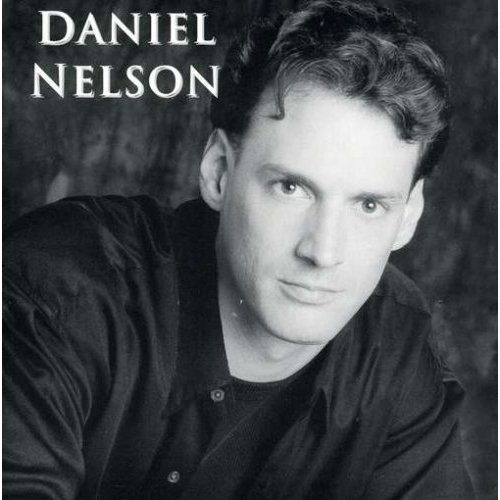

コメント