リチャード・カーペンター。1946年10月15日生まれ。
カーペンターズのヴォーカル&ピアノ、キーボード担当。
カレン・カーペンターの兄であり、いつも隣でピアノを弾いている人。
一般的にリチャード・カーペンターといえば、そんなイメージだろう。
今日はせっかく誕生日を迎えた尊敬する音楽家リチャードについて書こうと思う。

その前に皆さんが思うカーペンターズのイメージといえば
◆学生時代、英語や音楽の授業で歌ったグループ
◆子供向けの番組でかかっていた音楽
◆カレン・カーペンターの綺麗な歌声
◆誰もが一度は聴いたことがある音楽
◆兄と妹2人組のポップ・デュオ
こんなところだろうか。
確かにどれもその通りだが、本人の意思に反してメインでヴォーカルを務めたカレンにどうしてもスポットが当たりやすく、既にこの世を去ってから40年近く経ち、その原因からも伝説的ヴォーカリストとして語られて来た部分が多い。
カレン・カーペンターが優れたヴォーカリストであったことは今更ここで私が語る必要もないと思うが、それに比べて・・・と言わざる得ないぐらいリチャード・カーペンターの評価がイマイチ低い・・・いや、評価されていても、どうしてもカレンという天才ヴォーカリスト(陳腐な言葉だが、それ以外に見つからない)がフィーチャーされてしまい、その影に隠れがち。
彼の実力からすればもっと評価されて良いと私は考える。
ではなぜそう思うのか?
Contents
1.ピアニスト、キーボーディストとしてのセンス
リチャードのピアニストとしてのバックボーンはクラシックであり、ジャズである。
相応のテクニックを持ち合わせていながら、決してそれをひけらかす様な事はしない。
「自分を殺して抑える」というような自己犠牲の精神ではなく、何より大事にしているのがメロディであり、歌なのだからその為に何をするかを考えた上で、その場面場面で最適と思われるアプローチをする。
その証拠に彼らの曲のピアノに注意して聴いてみてほしい。
カレンが歌う後ろでリチャードは淡々と4分音符や8分音符で刻み続けるだけのアプローチがとても多いのだ。
4分、8分とはなんぞや?という方は『Yesterday Once More』を聴いてみていただきたい。
イントロから4分音符を刻み続け(しかもイントロはEコード1発!の上、たったの1小節!!)、ヴァースに入っても「It made me smile〜」までは基本的に4分音符を弾き続けるシンプルさ。
この「淡々とプレイする」が実は多くのプレイヤーが出来ない。
なぜならば、プレイヤーの自己表現手段は楽器だからだ。
大なり小なり”自分”を主張するには楽器を目立たせる(良いか悪いか別としてリスナーの耳を惹きつけるようなプレイをする)事が必要になる。
歌が主体であればあるほど、ポップであるほどその行為は一歩間違えれば一番の主役である歌の主役としての立ち位置を奪うどころか、それによって楽曲の雰囲気そのものが崩壊しかねない諸刃の剣とも言える部分を孕んでいる。
もちろんハード・ロックのように楽器とヴォーカル、または楽器同士のサウンド、プレイがまるで喧嘩しているが如くバトルを繰り広げ、激しく熱っぽいところも相まってカッコ良さを生み出し、聴き手の感情が高揚する部分に結びつくジャンルもある。
しかし、ことポップスに関しては歌とメロディが生命線とも言える中でリチャードは必要とあらば、いの一番にシンプルなプレイを”選択出来る”プレイヤーである。
これは非常に勇気と見極める目=センスが必要で、特にギターやピアノのようなコード楽器(和音楽器)のプレイヤーは自分のプレイに対して「果たしてこれ(こんなにシンプル)でいいのか」という気持ちになりがち。
または「ついつい・・・」という事で本来ならやらなくてもいい、やってはいけない所で必要のないプレイをしてしまうものだ。
そこにはシンプル=つまらないプレイに思われないかという不安か、もしくは「よし、ここで俺が一発目立ってやろう」という欲のどちらかがどうしても出てしまう。
幸いにして、私は根っからのベーシスト気質なので、そのような気持ちにはあまりならないのだが・・・。
多くのプレイヤーはそんなアプローチを選択してしまうのだ。
しっかり歌に寄り添ったプレイに聴こえるのはダイナミクスの付け方、要するに強弱のつけ方が激しい、それだけ感情込めて意図的にそうしてプレイしているのが伝わるからである。
実際にカーペンターズの楽曲は音量の起伏が激しいことに気づく方も多いと思う。
ロックになるとイントロからアウトロまで音量が平坦な場合が多いが、まるでクラシックを聴いているが如く、1曲の中で山あり谷ありの音量差である。
それにオーケストレーションが加わるものだから、余計にその部分が強調される。
実はカレンもそれに呼応するように歌っているのは言うまでもない。
ずっと聴いていても疲れにくいのは、生楽器にこだわり、そうしたギミックが施されているからではないだろうか。
一定の音量を保つ曲と起伏が激しい曲を同じ時間だけ聴き続けたら、疲れ方に差が出てくると思う。
疲れ方を考慮して楽曲作っている訳ではないだろうが、聴き手が感じる心地好さというのは多少なりとも作り手は意識するはずである。
何より、起伏がある事で聴き手の感情を揺さぶる効果に影響を与えている点は大きい。
2.アレンジャーとしてのセンス
カヴァー曲をリチャードの優れたアレンジによって”自分達の色”に染めてしまうのが、やたらと上手い点である。
他人が作った曲でも、まるで最初からカーペンターズのオリジナル曲として聴こえてしまうほど全く違和感がないどころか馴染んでしまっている。
さらに付け加えるならば、それを元曲以上、原作者が思いつかなかったアレンジを施してしまうのがリチャードの凄さでもある。
通常、カヴァーというのは「どんなに優れていてもオリジナルを超えることは無い」と評されがちで評価として不利になる事が多い中で、カヴァーの多いカーペンターズ=リチャードのアレンジ力というのは、そういった概念に当てはまらず、むしろオリジナルを凌駕しているとさえ言われるような馴染み方を提示出来る能力は桁外れだ。
例えばバート・バカラック作の『Close To You』などは原曲が「タタタタ」というスクエアなビートであるのに対してリチャードは「タッタタッタ」という跳ねたビートにリズムのノリ自体を変換してしまう。
この1発だけで決まり!というぐらい強烈なパンチである。
そして最後はカレンとのハーモニーが素晴らしい「Wa—-」というコーラスワーク、締め方としては大胆で斬新。
バカラック子飼いのディオンヌ・ワーウィックが、この曲を歌った時でさえもビートは同じくスクエアなので、恐らくこの曲をバート・バカラック本人が最初に聴いた時は自身の曲なのに「やられた!」と思った事だろう。
このような感じでリチャードの「どうすればその楽曲がより良くなるのか」という観点で練られているアレンジは、それを表現するアイディアが頭の中でかなり豊富にあるように思える。
数あるヒット曲の中でもカヴァーが比較的多いのが何より証明されていると思う。
We’ve Only Just Began
Superstar
Rainy Days and Mondays
It’s Going to Take Some Time
This Masquerade
Sweet Sweet Smile
I Won’t Last A Day Without You
Solitaire
Hurting Each Other
For All We Know
Touch Me When We’re Dancing
(They Long to Be)Close to You
他にもたくさんあるがベスト盤にも入るような有名曲でもカヴァーはこれだけある。
その他アルバムの中にも多くのカヴァーが含まれており、アルバムを作るにあたって充実した内容にしようと思った場合、他者の作品でも積極的に取り上げて構成するというのは作品クオリティを保つ為に欠かせない要素だったのだろう。
※リチャード本人も話しているように「アルバム曲の頭数が足らなくて仕方なくカヴァー曲を取り上げた」みたいな曲もたまには存在するが、そこも人間臭くて悪くない。
それでも、その辺のアルバムより圧倒的にクオリティが高いのだから。
そしてもう1曲取り上げておきたいのが『Goodbye To Love』。
バラードの中で歪み、それもヒステリックなトーンを持つファズ(音を変える機械)を効かせたギターを組み合わせたというのは、そういう前例がなかった・・・・少なくとも一般に浸透していなかった中で大々的にフィーチャーしたアレンジは賞賛に値する。
今となっては珍しくも何ともなくとも、この当時にやった事に意味がある。
いつだって1から10、1から100を作り上げるより全く無の0から1を作り出す方が価値があるのだ。
おかげで今日にも通じる「パワー・バラード」のような言葉が浸透。
この曲の注目すべきはもう一つ。
それはイントロが無いところ(というアレンジ)だ。
『Hurting Each Other』も同様で、楽曲の頭部分をすぐに歌い出しで始めるというアレンジはビートルズのジョン・レノンが作る曲にも良く見られる手法だが、イントロがあると思い込んでいる聴き手には意外性と、その後のメロディが強調されて、よりインパクトを与える効果として効き目がある。
この辺りも必要が無いなら思い切って省く事を厭わない、という姿勢は私もかなり影響を受けた。
カレンを天才ヴォーカリストと評するならば、必ずリチャードも天才アレンジャーであると同時に評価してほしいものだ。
3.ヒットを見極める目
有名な話だが『We’ve Only Just Began』なんて銀行のCMソング、つまり楽曲のたった一部分だけを聴いて「ヒット曲になる!」という確信を持ち、作者のロジャー・ニコルスに電話したという話から嗅覚というか、目の付け所が人より優れていたというエピソードだろう。
売れた曲、定番曲のみのカヴァーで構成しているならまだしも、まだ世の中に浸透していない曲を取り上げてヒット曲を作り出してしまう手腕は本当に凄い。
それにカヴァー曲のヒットが多いというのはリチャードの目の付け所の良さを表しているのは言うまでもないだろう。
専門的なことを書くと音楽関係者の方のみにしか話が通じなくなってしまうので、そうではなく音楽的なことはよく分からないという方でも音楽家としてリチャードの優れている点やカーペンターズをより楽しんでいただけるようにと彼の誕生日だったという事もあり、今回最も取り上げたかった点を思いつきで書いてみた。
実はヴォーカリストとしても優秀なリチャード
実は意外とロックなアプローチをするリチャード
など、まだまだたくさん取り上げたい部分や語れることはあるが、文字数も多くなってきたので今回はこの辺りで。
またご要望や機会があればカーペンターズに触れてみたい。
モッズ野郎サガワトモユキが参加するポップスバンド、ザ・ナイト・フライヤー(通称:ナイフラ)関連ページはこちらからどうぞ。60’Sアメリカン・ポップス、フレンチ・ポップス、AOR、MOR、シティ・ポップス、ソフト・ロックファンへ贈る!!
ナイフラOfficial HP

ナイフラOfficial YouTubeチャンネル「ナイフラチャンネル」
ナイフラOfficial twitter https://twitter.com/the_night_flyer
ナイフラOfficial Blog http://ameblo.jp/thenightflyer/
サガワトモユキOfficial Instagram https://www.instagram.com/the_night_flyer_60s/
毎回ナイフラの最新情報が届くメルマガ登録、ライブチケット予約、お問い合わせ、メンバーへの質問コーナー「ナイフラQ」もこちらへ↓


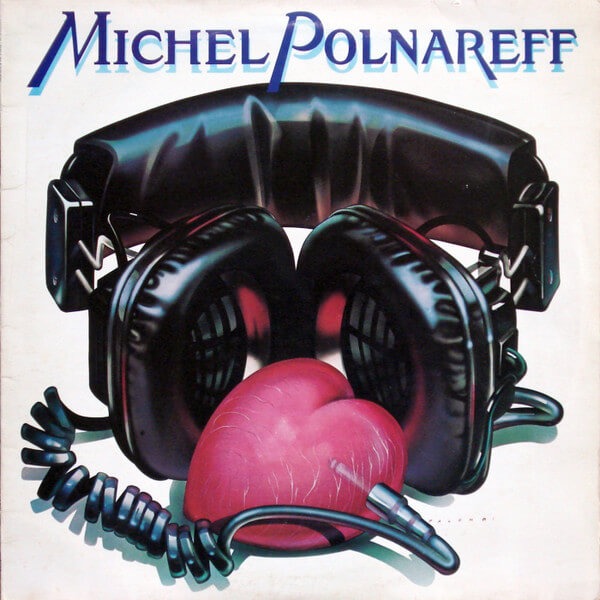

コメント